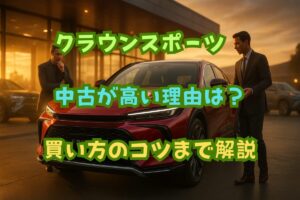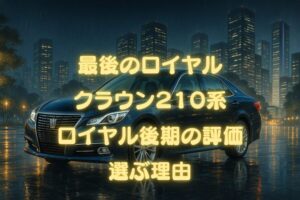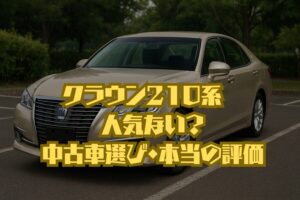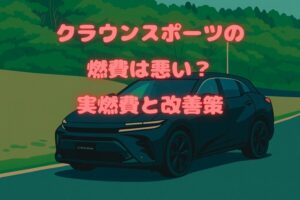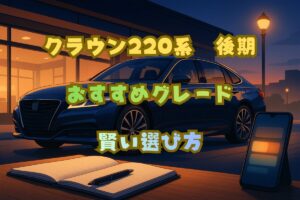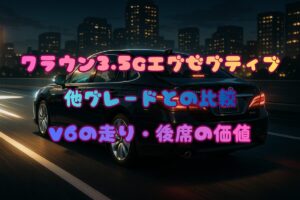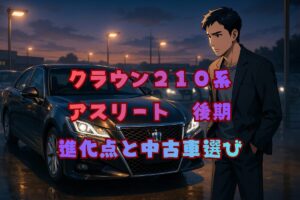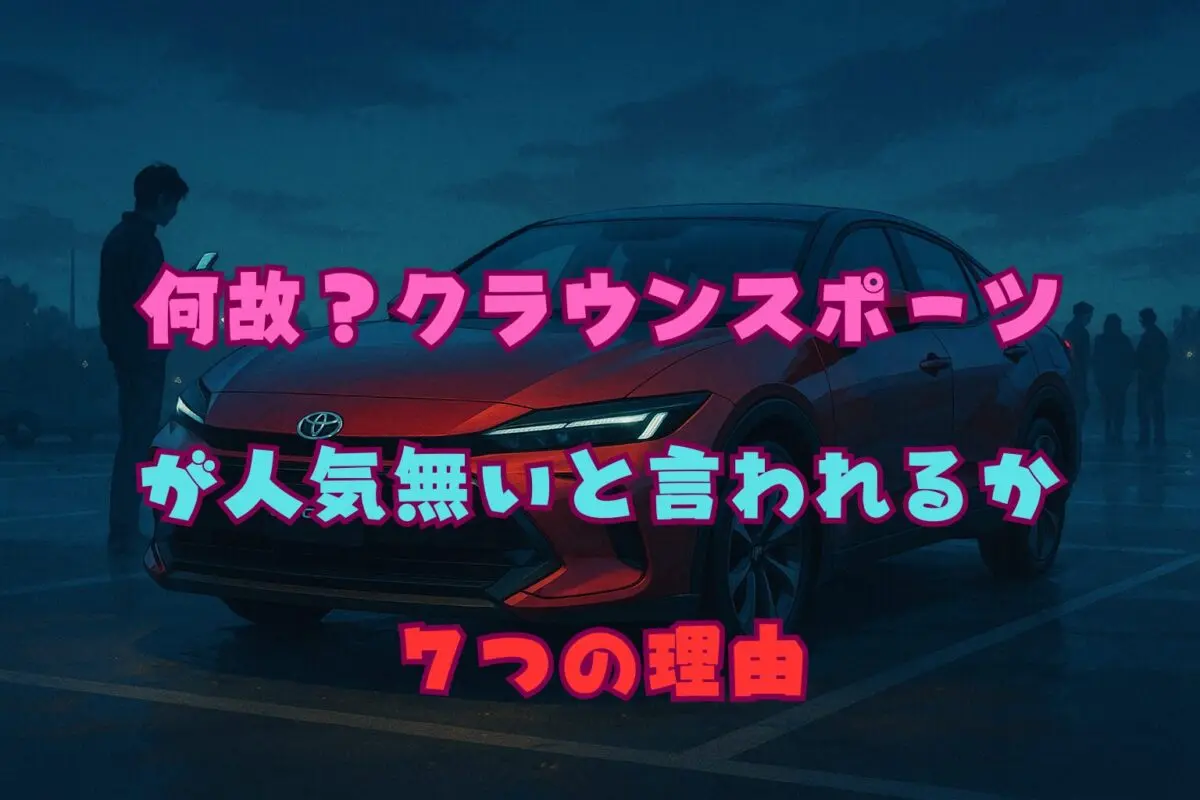2025年、誕生70周年を迎えたトヨタ・クラウン。40代以上の男性にとって、歴代クラウンは単なる高級車ではなく、憧れであり、誇りであり、まさに特別な「王冠」として輝き続けてきました。
この記事では、最新の「人気ランキング」を発表するとともに、単なる順位付けでは終わらせません。なぜその「クラウン世代」が選ばれたのか?人々を熱狂させた「デザイン」の魅力、しびれるような「走り」、そして圧倒的な「乗り心地と高級感」。
「あのモデルは本当にかっこいい」「走りが最高だったのはこの世代だ」—。 そんな皆様の熱い思いに応えるべく、各世代クラウンの特徴と人気の理由を、あらゆる角度から徹底比較します。70年の歴史が紡いだ、それぞれの「王冠」が持つ本当の「真価」に迫ります。
記事ポイント
- どの世代のクラウンが最も人気があるのかという総合ランキング
- デザイン、走り、高級感といった目的別に最も評価の高い世代
- 中古車市場での現在の人気やリセールバリュー(資産価値)
- 今後値上がりが期待できる「25年ルール」対象モデルなどの将来性
▼聴くブログ記事(本ブログ記事)はこちらより
歴代クラウン人気ランキング【2025年決定版】時代が選んだ「王冠」の真価
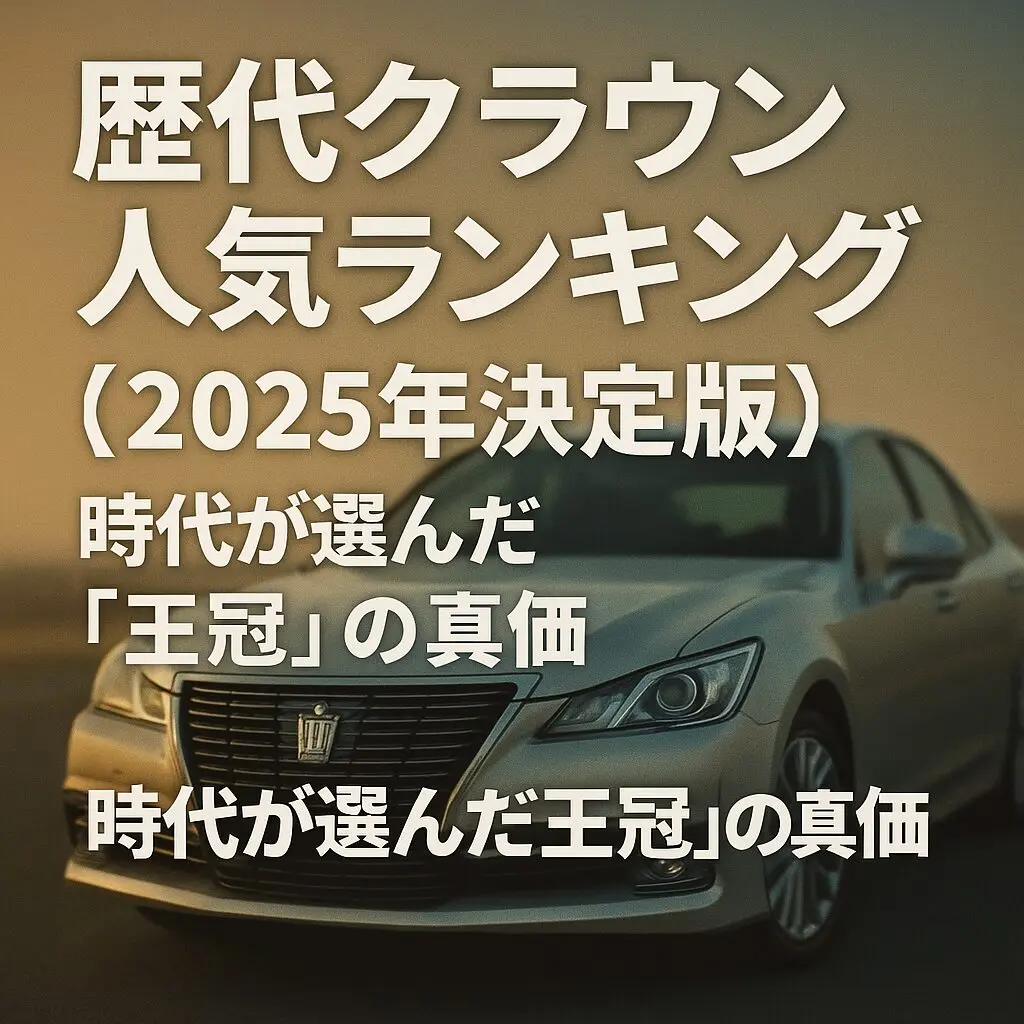
- 歴代クラウン人気ランキングTOP10【2025年最新版】
- 各世代クラウンの特徴と人気の理由
- デザインがかっこいいと評判のクラウン世代
- 「走りが最高」と支持されたスポーティ系クラウン
- 乗り心地と高級感で選ばれるモデルとは?
- 名車として語り継がれる「ゼロクラウン」の魅力
- 旧車ファンが選ぶ思い出のクラウンベスト3
歴代クラウン人気ランキングTOP10【2025年最新版】

我々が持つ「思い出補正」だけでなく、現代の中古市場での人気、デザインの普遍性、そして歴史的な価値を総合的に評価した、2025年最新版の人気ランキングを発表します。
- 1位:12代目(180系)「ゼロクラウン」(2003年~2008年)
- 選定理由: すべてをゼロから見直し、「伝統」という名の呪縛を自ら断ち切った最大の革新モデル。「静」から「動」への劇的な変貌は、クラウンの顧客層を劇的に若返らせ、今なお色褪せないデザインと走行性能で頂点に君臨します。
- 2位:15代目(220系)(2018年~2022年)
- 選定理由: ニュルブルクリンクで鍛え上げた、クラウン史上最もスポーティな「最後の純FRセダン」※。日本の道幅に最適化された全幅1800mmを守り切った集大成として、その価値が再評価されています。
※2位 15代目(220系):16代目にもセダン(FR)は存在しますが、伝統的な国内専用設計セダンの流れとしては15代目が一つの区切りと評価されています。
- 選定理由: ニュルブルクリンクで鍛え上げた、クラウン史上最もスポーティな「最後の純FRセダン」※。日本の道幅に最適化された全幅1800mmを守り切った集大成として、その価値が再評価されています。
- 3位:8代目(130系)(1987年~1991年)
- 選定理由: バブル経済という時代の頂点で輝いた、豪華絢爛の象徴。V8エンジンの搭載、エアサス、マルチビジョンなど、当時の最先端技術を惜しみなく投入し、「クラウンの威厳」を決定づけたモデルです。
- 4位:初代(RS型)(1955年~1962年)
- 選定理由: すべてはここから始まった、日本初の純国産乗用車。「観音開きドア」は、日本の自動車史の生きた伝説であり、その歴史的価値は計り知れません。
- 5位:14代目(210系)(2012年~2018年)
- 選定理由: 「ピンクのクラウン」という衝撃的な登場とは裏腹に、内装の質感や静粛性は歴代随一との呼び声も高いモデル。最後の「マジェスタ」がラインナップされた世代でもあります。
- 6位:16代目クラウン スポーツ(2023年~)
- 選定理由: 「これはクラウンなのか?」という賛否両論すら飲み込む、美しいクーペSUVデザイン。PHEVモデルの追加もあり、新たなクラウンファンを最も獲得している現代のヒット作です。
- 7位:7代目(120系)(1983年~1987年)
- 選定理由: 「いつかはクラウン」という伝説的なキャッチコピーを生んだ名車。クリスタルピラー※に象徴される、80年代の洗練された高級感を体現しています。
※7位 クリスタルピラー:ハードトップモデルのCピラー(後部座席横の柱)に採用された、樹脂製の透明感ある装飾。
- 選定理由: 「いつかはクラウン」という伝説的なキャッチコピーを生んだ名車。クリスタルピラー※に象徴される、80年代の洗練された高級感を体現しています。
- 8位:6代目(110系)「鬼クラ」(1979年~1983年)
- 選定理由: 直線基調の厳つい(いかつい)フロントマスクから「鬼クラ」の異名を持つ。旧車ファンからの支持が絶大で、80年代の不良(ワル)な魅力と高級感を両立しています。
- 9位:13代目(200系)(2008年~2012年)
- 選定理由: ゼロクラウンの正常進化版。アスリートとロイヤルの個性をより明確にし、先進の安全装備を搭載するなど、180系の革新を「完成」へと導いたモデルです。
- 10位:16代目クラウン クロスオーバー(2022年~)
- 選定理由: クラウン70年の歴史で初めて「セダンではない」スタイルをメインに据えた革命児。賛否はあれど、クラウンを未来へ繋ぐという重責を担ったモデルとしてランクイン。
各世代クラウンの特徴と人気の理由

ランキング上位のモデルたちは、なぜそれほどまでに人々を惹きつけるのでしょうか。クラウンの歴史は、「守るべき伝統」と「打ち破るべき常識」との戦いの歴史でもあります。各時代の特徴と、人気を博した背景を深掘りします。
初代~5代目:日本の「高級車」の基礎を築いた時代
- 初代(RS型)の功績
- 純国産への挑戦: 海外技術の模倣が当たり前だった時代に、トヨタ独自の技術で開発。
- 耐久性の証明: タクシーやハイヤーとして過酷な使用環境で鍛えられ、「壊れないトヨタ」の礎を築きました。
- 人気の理由: まさに日本のモータリゼーションの「始まり」そのものであり、歴史的価値が圧倒的です。
- 3代目(MS50型)の転換
- 「白いクラウン」の衝撃: それまで公用車・社用車の「黒」が常識だった中、「白」を打ち出し、個人オーナー(自家用車)という市場を爆発的に開拓しました。
- 人気の理由: 日本人にとって、クラウンが「会社の車」から「自分の車=憧れ」へと変わった、価値観の転換点です。
6代目~9代目:「いつかはクラウン」の黄金期
- 7代目(120系)の象徴
- 「いつかはクラウン」: 高度経済成長を経て豊かになった日本人の夢の象徴となりました。
- 技術革新: 国産初のスーパーチャージャー搭載など、技術的にも意欲的でした。
- 人気の理由: 40代以上の男性が幼少期・青年期に最も憧れた、「成功の証」としてのイメージが色濃く残っています。
- 8代目(130系)の絶頂
- バブルの体現: 4.0L V8エンジンの搭載、豪華な内装、ハイテク装備。まさにバブル景気の絶頂期を象徴する「全部盛り」の豪華さです。
- 人気の理由: 「日本が最も輝いていた時代」の高級車像を完璧に体現しており、その圧倒的な存在感は今なお語り草です。
12代目~15代目:伝統との決別と「走り」の追求
- 12代目(180系)「ゼロクラウン」の革命
- すべてを一新: プラットフォームからエンジン(直6→V6)まで、すべてをゼロから開発。
- 「アスリート」の確立: 走りを重視した「アスリート」が主役となり、保守的なイメージを払拭。
- 人気の理由: それまでクラウンに興味のなかった若い世代を振り向かせた、デザインと走りの「大革命」。この功績が、人気No.1の最大の理由です。
- 15代目(220系)の熟成
- 走りの集大成: 「ニュルブルクリンク」での徹底的な走り込み。
- 国内専用設計: 全幅1800mmという日本の道路事情に最適化されたサイズ感。
- 人気の理由: スポーティな外観と、日本のための高級セダンとしての「最後の砦」という存在価値が高く評価されています。
15代目クラウンはトヨタ初のコネクティッドカー(DCM標準)として公式発表されています。[公式リリース:15代目クラウン、DCM標準搭載]
16代目(現行):多様化する時代への「挑戦」
- 4つのボディタイプ: クロスオーバー、スポーツ、セダン、エステートという前代未聞のラインナップ。
- グローバル化: 日本専用車という立場から、世界40カ国以上で販売されるグローバルカーへ。
- 人気の理由: 賛否両論こそが、クラウンが「挑戦」を止めない証。特に「スポーツ」はデザインで新たなファンを獲得し、クラウンの未来を切り開いています。
4つのボディタイプ(クロスオーバー/スポーツ/セダン/エステート)はトヨタ公式の世界初披露で明確化され、約40の国と地域で展開されることが発表されました。
[公式リリース:Crown 4モデル世界初公開(Toyota Global Newsroom)]
さらに70周年の節目としてエステートの国内導入が発表され、シリーズ化の狙いと歴史文脈も公式に整理されています。
[公式リリース:Crown Estate発表:70周年の位置づけ(Toyota Global)]
デザインがかっこいいと評判のクラウン世代

クラウンの歴史は、その時代の「かっこよさ」を定義してきた歴史でもあります。保守的と言われながらも、時折、時代の常識を覆すような衝撃的なデザインを生み出してきました。ここでは、特にデザイン性が高く評価される世代をピックアップします。
- 【第1位】15代目(220系)
- 「クラウン史上最もスポーティ」と評される、低く構えたワイド&ローなシルエット。
- シャープに切れ上がったヘッドライトと、大胆な造形のフロントグリルは、伝統的なクラウンオーナー層を驚かせると同時に、多くの若者層を魅了しました。
欧州のプレミアムセダンと真っ向から渡り合うという、トヨタの本気度がデザインに現れています。「クラウンらしさ」を全面に出した最後のモデルとして、その完成度を支持する声が多数です。
- 【第2位】12代目(180系)「ゼロクラウン」
- 「静から動へ」のテーマを体現した、洗練された直線基調のデザイン。
- それまでの丸みを帯びた重厚長大なイメージを払拭し、シャープで知的なアスリート像を確立しました。
デビューから20年以上経過した今見ても、全く古さを感じさせない普遍的なかっこよさがあります。特にアスリートグレードの専用デザインは、カスタムベースとしても絶大な人気を誇りました。
- 【第3位】8代目(130系)
- バブル期ならではの「威厳」と「豪華さ」を兼ね備えたデザイン。
- 7代目の洗練されたイメージをブラッシュアップし、より重厚感と高級感を高めたスタイルは、まさに当時の「成功者の象徴」でした。
若者層から見れば「古い」デザインかもしれませんが、40代以上の男性にとっては、経済成長の頂点を知る「黄金時代のかっこよさ」が凝縮されています。
- 【第4位】16代目クラウン スポーツ
- セダンの枠を完全に飛び越えた、流麗なクーペSUVスタイル。
- シャープなハンマーヘッドデザインと、大きく張り出したリアフェンダーが織りなす躍動感は、従来のクラウンユーザー以外からも「素直にかっこいい」と評価されています。
「これがクラウン?」という戸惑いを、「これが新しいクラウンだ」という納得に変えるだけのデザイン的説得力を持っています。
- 【第5位】4代目(MS60系)「クジラクラウン」
- 丸みを帯びた「スピンドルシェイプ(紡錘形)」という、あまりにも革新的なデザイン。
- 当時はその奇抜さから保守層に受け入れられず、商業的には失敗とされました。
時代を先取りしすぎた悲運のモデル。しかし、その唯一無二のデザインは50年の時を経て再評価され、現在では旧車ファンから「時代を超えたかっこよさ」として熱烈に支持されています。
「走りが最高」と支持されたスポーティ系クラウン

かつてクラウンといえば、「おじさん車」あるいは「後席に乗る車」というイメージが先行していました。
しかし、その常識を自ら打ち破り、「運転が楽しい車」としての評価を確立したモデルが存在します。ここでは、「走り」にこだわるドライバーから最高評価を得た、歴代のスポーティ系クラウンを紹介します。
- 【第1位】12代目(180系)「ゼロクラウン」(2003年~2008年)
- まさに「静から動へ」のキャッチコピーを体現した革命児です。
- 新プラットフォームとV6エンジン: 伝統の直列6気筒エンジンと決別し、低重心のV型6気筒エンジンと新開発プラットフォームを採用。これにより、ハンドリングは劇的にシャープになりました。
- 欧州セダンに匹敵: それまでの日本の高級車特有のフワフワした乗り味を一掃。良くも悪くも「日本的」だったクラウンが、欧州のプレミアムセダンと真っ向から渡り合えるスポーティな乗り味を手に入れたのです。
「走る楽しさ」という新たな価値観をクラウンにもたらした功績は計り知れません。40代以上のドライバーが「クラウンを見る目が変わった」と実感した最初のモデルでしょう。
- 【第2位】15代目(220系)(2018年~2022年)
- 「走り」の追求を極限まで高めた、歴代史上最もスポーティなFRセダンです。
- ニュルブルクリンクでの開発: 開発の聖地、ドイツの過酷なサーキット「ニュルブルクリンク」で徹底的に鍛え上げられました。
- FRの集大成: 「走る・曲がる・止まる」という車の基本性能を根本から見直し、ドライバーの意のままに操れる正確なハンドリングを実現。
ゼロクラウンが蒔いた「走り」の種を、15年の歳月をかけて「FRセダンの集大成」として花開かせたモデル。その本気度は、走り好きのベテランドライバーほどうなるものがあります。
- 【第3位】16代目クラウン スポーツ(2023年~)
- 新時代の「スポーティ」を定義する一台です。
- SUVの常識を超える走り: 「新しいカタチのスポーツSUV」として、俊敏でスポーティな走りを実現。
- PHEVの圧倒的パワー: 特に2.4LターボPHEVモデルの走りは、国産SUVトップクラスとの呼び声も高く、環境性能と運転する楽しさを見事に両立させています。
「硬いだけがスポーツじゃない」という開発思想のもと、しなやかな足回りと意のままの操縦性を両立。これはFRセダンとは異なる、AWD※時代の新たな「走る楽しさ」の提案です。
※AWD:全輪駆動(All-Wheel Drive)。4輪すべてに駆動力を伝え、高い走行安定性を生む方式。
乗り心地と高級感で選ばれるモデルとは?
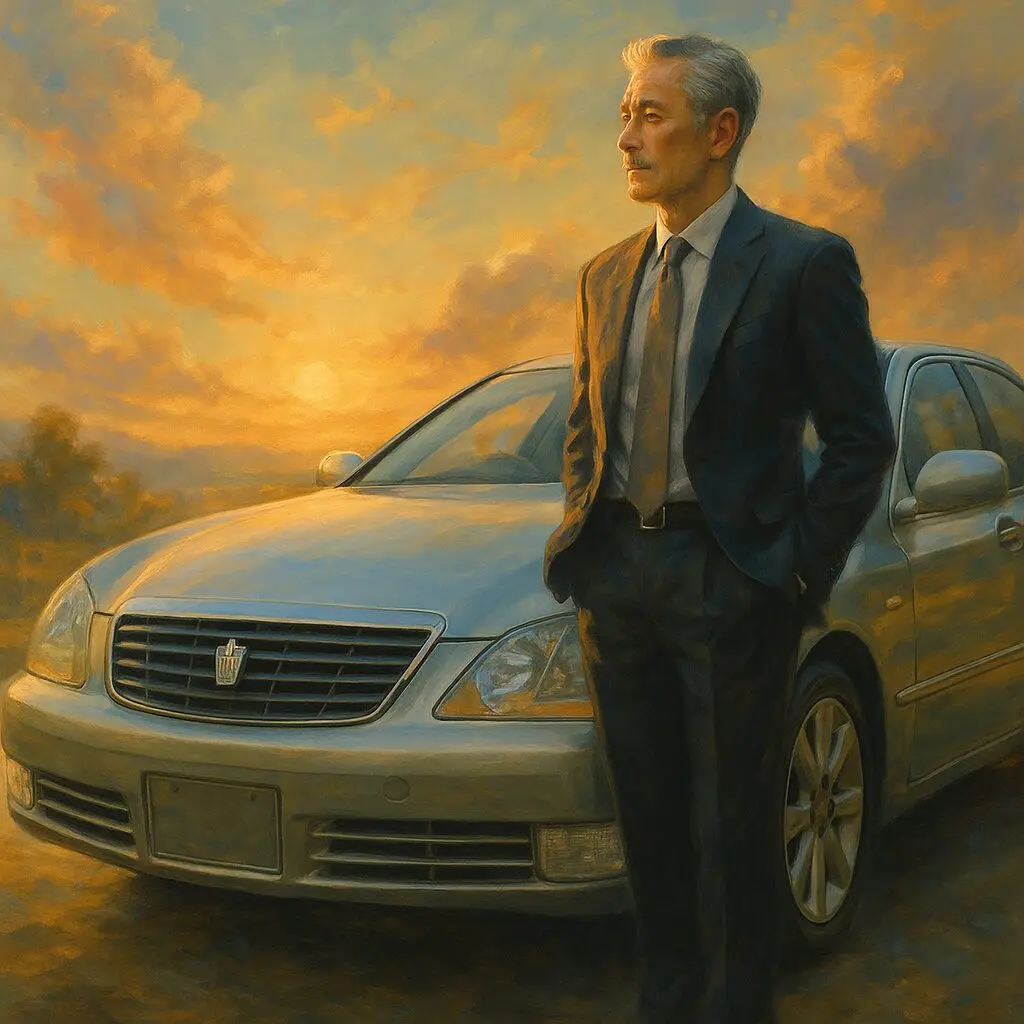
スポーティな走りと対極にある、クラウン本来の魅力。それは、乗る人すべてを包み込む「静粛性」と「上質な乗り心地」、そして細部に宿る「高級感」です。ここでは、「これぞクラウン」と呼ぶにふさわしい、伝統的な価値観で選ばれるモデルを紹介します。
- 【第1位】14代目(210系)(2012年~2018年)
- 中古市場において、今なお「内装の高級感は歴代随一」との呼び声が非常に高いモデルです。
- 質感の高いインテリア: 220系がスポーティさに振った分、210系の(特に後期型)重厚で質感の高い内装デザインが再評価されています。
- 静粛性と重厚感: ゼロクラウン以降のスポーティさを継承しつつ、クラウン伝統の静かで滑らかな乗り心地を高次元で両立。
最後の「マジェスタ」がラインナップされた世代でもあり、伝統的な高級セダンとしての「完成形」を求める層から絶大な支持を受けています。
- 【第2位】9代目(JZS140系)(1991年~1995年)
- この世代最大の功績は、クラウンのヒエラルキーの頂点に「クラウンマジェスタ」を誕生させたことです。
- 世界レベルの快適性: マジェスタは専用のモノコックボディと4輪ダブルウィッシュボーンサスペンションを採用し、当時「世界最高レベル」と称された静粛性と快適な乗り心地を実現しました。
バブル崩壊期の混迷の中、「品格」と「静けさ」という新たな価値で、日本の高級車の基準をさらに引き上げたモデルです。
- 【第3位】7代目(MS125型)(1983年~1987年)
- 「いつかはクラウン」という名キャッチコピーと共に、日本中が憧れた高級感の象徴です。
- クリスタルピラー: ハードトップモデルに採用された、光を反射する樹脂製のCピラー。その輝きは、80年代の洗練された「ゴージャス感」を演出しました。
性能的な高級感だけでなく、視覚的に「分かりやすい豪華さ」で人々の心を掴みました。40代以上の男性の記憶に「成功の象徴」として深く刻まれている一台です。
名車として語り継がれる「ゼロクラウン」の魅力

総合人気ランキングで堂々の1位に輝いた12代目(180系)。なぜこのモデルは単なる人気車を超え、「名車」として語り継がれるのでしょうか。それは、クラウン70年の歴史において、最も劇的な「革命」を成功させたからです。
- 1. すべてをゼロから見直した「覚悟」
- 「ZERO CROWN(ゼロクラウン)」という開発テーマは、伊達ではありませんでした。プラットフォーム、エンジン、サスペンションという車の骨格すべてを一新。
- 「かつてゴールだったクルマが、いまスタートになる。」というキャッチコピーは、トヨタが「伝統」という名の重い鎖を自ら断ち切るという、強い覚悟の表れでした。
- 2. クラウンの歴史を塗り替えた「デザイン革命」
- それまでの丸みを帯びた保守的なデザインと決別。シャープで直線的な、躍動感あふれるスポーティな外観は、衝撃的ですらありました。
- クラウンの象徴である王冠エンブレムの書体までも刷新し、「新しいクラウン」の誕生を視覚的に強く印象付けました。
- 3. 「走り」という新たな価値観の提示
- 伝統の直列6気筒からV型6気筒エンジンへ全面移行。これにより、フロントの重量が軽くなり、ハンドリング性能が劇的に向上しました。
- 欧州のプレミアムセダンに匹敵するスポーティな乗り味は、「クラウン=おじさん車」というイメージを完全に払拭しました。
- 4. 「アスリート」と「ロイヤル」の二極化に成功
- 走りを追求する「アスリート」と、伝統の快適性を守る「ロイヤル」。この2つのグレードの個性を明確に分けたことで、それまでクラウンに見向きもしなかった若い世代の獲得に成功しました。
ゼロクラウンは、クラウンが「過去の栄光に安住する車」ではなく、「未来を切り開く挑戦者」であることを証明した、歴史的な転換点です。このモデルの成功がなければ、現在の多様なクラウンの姿は存在しなかったでしょう。
旧車ファンが選ぶ思い出のクラウンベスト3

性能や燃費、合理性だけでは車は語れません。特にクラウンは、その時代の空気や人々の夢を乗せて走ってきました。ここでは、旧車ファンの間で今なお熱く語り継がれる、「思い出」という名の価値を持つ名車ベスト3を紹介します。
- 第1位:4代目(S60/70系)「クジラクラウン」(1971年~1974年)
- 「クラウン史上、最も偉大な失敗作」
- 丸みを帯びた「スピンドルシェイプ(紡錘形)」と呼ばれる前衛的なデザインを採用。しかし、当時の保守的なオーナー層からは「奇抜すぎる」と受け入れられず、商業的には大苦戦しました。
時代を50年先取りしたデザインは、今や旧車ファンから「唯一無二の存在」として熱狂的に支持されています。「失敗」を恐れず挑戦したクラウンの革新性の象徴です。
- 第2位:8代目(S130系)(1987年~1991年)
- 「バブル経済という時代の頂点」
- 日本が最も輝いていた時代に登場。「満たされて、新しいクラウン」のコピー通り、エアサス、マルチビジョン、そしてV8エンジン搭載と、当時の最先端技術と豪華装備を惜しみなく投入しました。
40代、50代の男性が青年期に見た、最もきらびやかで「無敵」だった日本の象徴。その豪華さは、もはやロマンの域に達しています。
- 第3位:初代(RS型)(1955年~1962年)
- 「すべての始まり。日本の誇り」
- 海外メーカーの技術に頼らず、「日本人の手で、純国産車を造る」という夢を実現した、日本の自動車史の生きた伝説です。
最高速度100km/h、観音開きのドア。そのすべてが、戦後日本の「挑戦」そのものでした。旧車ファンにとって、これは単なる車ではなく、日本の自動車産業の「原点」として別格の存在です。
歴代クラウンの人気から紐解く「現代の価値」と「未来の展望」

- クラウンアスリート・ロイヤルシリーズの違い
- 中古市場で今も人気の高いクラウン世代
- リセールバリューが高いクラウンはどのモデル?
- 今後価値が上がる可能性のあるクラウンモデル
- 歴代クラウンのデザイン変遷と時代背景
- クラウン人気の移り変わりから見る日本の高級車文化
クラウンアスリート・ロイヤルシリーズの違い

クラウンの歴史を語る上で欠かせないのが、「アスリート」と「ロイヤル」という二大巨頭の存在です。特に12代目「ゼロクラウン」から14代目(210系)にかけて、この2つの個性は明確に分けられ、オーナーの「クラウン観」を二分してきました。
「走りのアスリート」か、「快適性のロイヤル」か。 これは、クラウンを選ぶオーナーにとって、自らのスタイルを表明する重要な選択でした。
- クラウンアスリート (Athlete) ※
- コンセプト: 「俊敏性・スポーツ走行」
- ターゲット: 運転を楽しみたいドライバー、若い世代
- 外観: メッシュ状グリル、専用バンパー、スポーティなアルミホイール、10mm低い車高
- 内装: ダークトーン基調、スポーツシート
- 走行性能: 専用スポーツサスペンション、大排気量エンジン(3.5L V6など)のラインナップ
- クラウンロイヤル (Royal) ※
- コンセプト: 「乗り心地・快適性」
- ターゲット: 伝統的なクラウンオーナー、後席の快適性を重視する層
- 外観: 横基調の格子状グリル、落ち着いたデザイン
- 内装: 明るい色調、ウッドパネル、快適性重視のシート
- 走行性能: 乗り心地を最優先にしたソフトなサスペンション、静粛性重視のエンジン
※アスリート:英語で「運動選手」の意。その名の通り、走行性能を高めたモデル。 ※ロイヤル:英語で「王室の」の意。クラウン本来の快適性や高級感を追求したモデル。
【考察】クラウンの二面性を支えた名コンビ
この明確な「住み分け」こそが、クラウンの顧客層を長年にわたり維持・拡大させてきたトヨタの巧みな戦略でした。
40代以上の男性であれば、若い頃に「アスリート」を選び、年齢と共に「ロイヤル」に乗り換える、といったクラウン内でのステップアップを夢見た方もいるでしょう。
この伝統的な住み分けは、14代目(210系)をもって最後となり、15代目(220系)からはアスリートが「RS」グレードに、ロイヤルが「標準グレード」に統合・再編されました。この二極化の時代こそ、クラウンが日本の高級車市場で最も輝いていた時代の一つと言えます。
中古市場で今も人気の高いクラウン世代

「いつかはクラウン」の夢を、今こそ中古車で実現したいと考える層は後を絶ちません。しかし、世代によって「人気」の質は大きく異なります。ここでは、2025年現在の市場動向から、特に人気の高い世代を目的別に紹介します。
- 【完成されたFRセダンの頂点】14代目(210系)
- 多くのユーザーから「内装の高級感が歴代で最も優れている」と評価される世代です。
- 人気の理由:
- 「アスリート」「ロイヤル」「マジェスタ」という伝統の3ラインが揃った最後の世代。
- トヨタセーフティセンスが搭載された後期型は、安全性と高級感を両立。
- 流通量が豊富で、価格帯も90万円~300万円と広く、予算に合わせて選びやすい。
現行モデルが大きく変貌した今、伝統的な「クラウンらしいクラウン」を求める層からの需要が集中しています。特に後期型アスリートは、デザイン、走り、高級感のバランスが最も取れたモデルとして根強い人気を誇ります。
- 【伝説の革命児をお手頃に】12代目(180系)「ゼロクラウン」
- クラウンの歴史を塗り替えた「名車」が、今や50万円前後から探せるようになりました。
- 人気の理由:
- V6エンジンと新プラットフォームがもたらす、色褪せないスポーティな走り。
- デビューから20年が経過しても古さを感じさせない、完成された直線基調のデザイン。
低予算で「走れる高級セダン」を体験したい若者層や、青春時代の憧れをもう一度手に入れたい40代以上の男性から、カスタムベースとしても含めて絶大な支持を得ています。
- 【高年式スポーティセダン】15代目(220系)
- デビューから5年以上が経過し、中古車市場での流通台数がピークを迎えています。
- 人気の理由:
- ニュルで鍛えたスポーティな走りと、初代コネクティッドカーとしての先進性。
- 新車価格が高額だった分、中古車での「お買い得感」が非常に高まっています。
210系よりも「走り」と「新しさ」を重視する層にとって、最も現実的で賢い選択肢となっています。
リセールバリューが高いクラウンはどのモデル?

「リセールバリュー(再販価値)」は、車を資産として捉える現代において、購入時の重要な判断基準です。驚くべきことに、現在最もリセールバリューが高いクラウンは、伝統的なセダンではありません。
- 第1位:16代目 クラウン スポーツ(2023年~)
- 圧倒的なリセール価値: 2025年現在、残価率82~85%という驚異的な数値を維持しています。
- 理由: 新車需要の高さに加え、世界的なSUVブーム、そしてPHEVを含むハイブリッド性能が海外(特にシンガポールやニュージーランドなど)で高く評価され、輸出需要が相場を強力に下支えしています。
- ポイント: グレードは「Z(ハイブリッド)」、人気カラーは「アッシュ(単色)」や「ブラック×アッシュ」が最強とされています。
- 第2位:16代目 クラウン クロスオーバー(2022年~)
- 安定したリセール: スポーツほどの爆発力はないものの、1年落ちで約80%、3年落ちでも約70%前後を維持する「安定型」のリセールを誇ります。
- 理由: セダンとSUVの融合という革新的なスタイルが国内外で評価されており、こちらも輸出需要が底堅いのが特徴です。
- 第3位:15代目(220系)(2018年~2022年)
- 健闘するセダン: SUVには及ばないものの、3年落ちの「ハイブリッド 2.5 RS アドバンス」で残価率71.6%を記録するなど、セダンとしては非常に優秀なリセールを維持しています。
「クラウン」の資産価値の地殻変動
このデータが示すのは、クラウンの資産価値が「セダン」という枠組みから、「SUV」という新たな価値基準へと完全に移行したという事実です。
40代以上の伝統的なオーナー層が求める「品格」とは別に、市場(特に海外市場)はクラウンの「SUVとしての性能」と「ハイブリッド技術」に最も高い価値を見出しています。
16代目スポーツの異常なリセールバリューは、トヨタの変革が「資産価値」という面において大成功であったことを証明しています。
今後価値が上がる可能性のあるクラウンモデル

「あの時、買っておけばよかった」。そう後悔する前に、将来の「お宝」になる可能性を秘めたクラウンを知っておくのも、ベテランの車好きの嗜みです。
リセールバリューとは異なる、「文化的価値」や「希少性」で今後値上がりが期待できるモデルを、プロの視点で予測します。
- 最注目:11代目(17系)アスリートV / エステート
- 理由: 2024年9月から、1999年式のモデルがアメリカの「25年ルール」※の対象となり始めました。
- 分析: 17系は、伝説的な名機「1JZ-GTE」型(2.5L直列6気筒ターボ)を搭載した最後のクラウンです。海外のJDMファンにとって、このエンジンを積んだFRセダンやステーションワゴン(エステート)は垂涎の的。すでにスカイラインGT-R(R34)等が凄まじい高騰を見せている通り、状態の良い17系アスリートVやエステートは、今後数年で国内相場が急騰する可能性が極めて高いです。
※25年ルール(NHTSA公式FAQ):製造から25年以上経過した車はFMVSS適合要件の対象外として輸入可能。[NHTSA Importation & Certification FAQs]。 - ネオ・クラシック:8代目(130系)V8モデル / ワゴン
- 理由: バブル期を象徴する豪華な「ネオ・クラシック」として、世界的に評価が高まっています。
- 分析: セルシオに先行して搭載されたV8エンジンモデルや、独特のスタイルを持つステーションワゴン(特にベンチシート&コラムシフト仕様)は、その希少性と時代性から価格が上昇傾向にあります。「あの頃」の日本の輝きを求める国内外のコレクターにとって、魅力的な投資対象となっています。
- 近代の名車:12代目(180系)「ゼロクラウン」後期型アスリート
- 理由: 「名車」として語り継がれるモデルは、程度の良い個体から必ず価値が上がります。
- 分析: デビューから20年が経過し、中古市場では安価な個体が増える一方、低走行で内外装が美しい「極上車」は急速に減少しています。クラウンの歴史を変えた革命的なモデルとして、その価値が再評価される時期は目前です。状態の良い個体を今のうちに手に入れ、大切に維持すること自体が、将来的な資産形成となる可能性があります。
歴代クラウンのデザイン変遷と時代背景

クラウンのデザインは、常にその時代の日本の「空気」と「価値観」を映し出す鏡でした。70年の変遷を、日本の歩みと共に振り返ります。
- 1950年代~1960年代:黎明期(初代~3代目)
- 時代背景: 戦後復興から高度経済成長へ。欧米に追いつけ追い越せの時代。
- デザイン: 初代(RS型)は、純国産ながらもアメリカ車の影響を色濃く受けた「観音開きドア」が特徴。3代目(MS50型)の「白いクラウン」は、公用車(黒)のイメージを払拭し、「個人が所有する憧れ=マイカー」という文化を創造しました。
- 1970年代:模索期(4代目~5代目)
- 時代背景: 安定成長とオイルショック。価値観が揺れ動いた時代。
- デザイン: 4代目「クジラクラウン」は、未来的なスピンドルシェイプで大いなる挑戦を試みるも、保守層に受け入れられず商業的に失敗。その反省から、5代目は重厚長大な「ザ・高級車」というべき保守的なデザインに回帰します。
- 1980年代:絶頂期(6代目~8代目)
- 時代背景: バブル経済。日本が世界No.1と信じた、自信と富に満ちた時代。
- デザイン: 6代目「鬼クラ」の直線的な威厳を経て、7代目(120系)は「クリスタルピラー」で洗練された豪華さを演出。そして8代目(130系)は、V8エンジン搭載の3ナンバー専用ボディとハイテク装備で、まさにバブルの頂点を極めました。
- 1990年代~2000年代:変革期(9代目~12代目)
- 時代背景: バブル崩壊と「失われた時代」。欧州車が台頭し、既存の価値観が陳腐化した時代。
- デザイン: 9代目で「マジェスタ」が誕生し、高級感が細分化。そして12代目「ゼロクラウン」が、すべてを破壊し再構築。「おじさん車」のイメージを捨て、欧州車と戦えるスポーティで直線的なデザインへと舵を切りました。
- 2010年代~現在:多様化期(14代目~16代目)
- 時代背景: SUVの世界的な台頭と、セダン市場の縮小。グローバル化と環境意識の高まり。
- デザイン: 14代目の「ピンクのクラウン」で若返りへの強い意志を示し、15代目はニュルで鍛えたスポーティデザインを極めます。そして16代目は、「セダン」という枠すら捨て、クロスオーバー、スポーツ、エステートという多様な姿へと「大転換」しました。
クラウン人気の移り変わりから見る日本の高級車文化

クラウンの人気の変遷は、そのまま日本の「高級車文化」と「成功の定義」の変遷でもあります。
- 1960~1980年代:「憧れの頂点」としての文化
- 3代目「白いクラウン」が、「自家用車」という文化そのものを牽引しました。
- 7代目・8代目の時代、「いつかはクラウン」という言葉がすべてを物語っています。日本人の成功の定義は「良い家に住み、クラウンに乗ること」であり、クラウンは富と社会的地位を示す、唯一無二の絶対的なステータスシンボルでした。
- 1990~2000年代:「選択する高級車」への文化変容
- バブル崩壊後、レクサス(セルシオ)の登場や、ベンツ、BMWといった輸入車が現実的な選択肢となりました。
- 「高級車=クラウン」という図式が崩れ、クラウンは「数ある高級車の一つ」へと変化します。
- 12代目「ゼロクラウン」の「アスリート」は、この時代に「あえてクラウンを選ぶ」理由、すなわち「輸入車にはない、日本の道に最適化されたスポーティさ」を提示することで、見事にファンの心を取り戻しました。
- 2010~2020年代:「アイデンティティを表現する」文化へ
- 40代以上の男性にとって、クラウンは「父親の車」から「自分の車」になりました。
- 「ロイヤル」を選ぶことは「伝統と快適性」を重んじる姿勢、「アスリート」を選ぶことは「走る楽しさ」を追求する姿勢、というように、グレード選びがオーナーのアイデンティティを表現する手段となりました。
- 現在(16代目):「ブランド」としての新たな文化
- 16代目の4モデル展開は、「クラウン=セダン」という定義の終焉であり、「クラウン=日本の高級ブランド」という新たな定義の始まりです。
- 考察: かつての日本人は「クラウンという頂点」を皆で目指しました。しかし現代の日本人は、「クラウン スポーツ」や「クラウン エステート」という多様な選択肢の中から、自分のライフスタイルに合う「王冠(クラウン)」を選びます。日本の高級車文化は、画一的な「ステータス」から、多様な「ライフスタイルの表現」へと成熟したのです。
歴代クラウン人気ランキング総括:我々が愛した「王冠」の誇りと未来
歴代クラウンの人気を様々な角度から分析すると、クラウンが単なる高級車ではなく、日本の時代そのものを映す鏡であったことがわかります。
かつては画一的な「成功の証」でしたが、今やその価値は多様化し、オーナーのライフスタイルを表現する存在へと進化しました。この記事で分析した、70年の歴史と未来への展望について、要点を箇条書きでまとめています。
- 総合人気1位はすべてを刷新した革新の「ゼロクラウン」(12代目)
- 2位は最後の純FRセダンと評されるスポーティな15代目(220系)
- 3位はバブル経済の豪華さを象徴する8代目(130系)
- デザイン評価が最も高いのは、歴代で最もスポーティな15代目(220系)
- 「走り」の評価を決定的に変えたのも「ゼロクラウン」の功績
- 乗り心地と高級感では、内装の質感が随一と評される14代目(210系)
- アスリートは「走り」、ロイヤルは「快適性」で明確に差別化されていた
- 旧車ファンには、時代を先取りしたデザインの「クジラクラウン」が根強く支持されている
- 中古市場では、伝統的なFRセダンとしての完成度が高い14代目(210系)が今も人気
- リセールバリュー最強モデルは、現行の16代目「クラウンスポーツ」
- 現代のクラウンの資産価値は、海外からの輸出需要に大きく左右される
- 今後価値が上がる可能性が最も高いのは、25年ルール対象となる17系「アスリートV」
- クラウンの歴史は、日本の経済成長と価値観の変化そのものである
- クラウン人気は画一的な「ステータス」から、多様な「ライフスタイルの表現」へと成熟した
- クラウンの真の伝統とは、形を守ることではなく「革新への挑戦」を続けることである
- クラウンスポーツの中古が高い理由は?後悔しない買い方のコツまで徹底解説
- クラウン220系にアスリートは無い?後継RSの全貌と中古購入完全ガイド
- 最後のロイヤル!クラウン210系ロイヤル後期の評価|今あえて選ぶ理由とは?
- 【2025年版】クラウン220系|前期・後期の違いを徹底比較!中古車の選び方から価格相場まで完全ガイド
- 「クラウン210系は人気ない?」は嘘!後悔しない中古車選びの全知識と本当の評価を徹底解説
- 【徹底解説】クラウンスポーツの燃費は悪い?実燃費と評判から具体的な改善策まで完全ガイド
- クラウン220系後期の中古車購入術。おすすめグレードと賢い選び方
- クラウン3.5Gエグゼクティブと他グレードの違いを比較!V6の走りと後席の価値
- 【徹底解説】クラウン210系アスリート後期の進化点と中古車選びの決定版
- クラウンクロスオーバーは不人気?後悔する前に知るべき辛口評価と真実